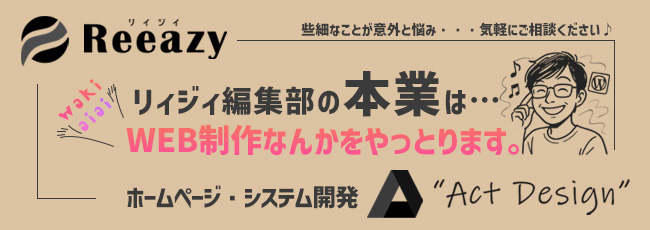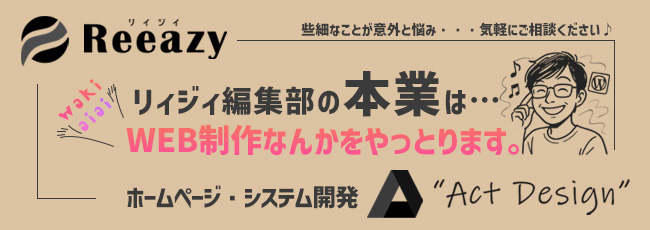
まず始めにお伝えしておきたいのは、わたしの作るチャーシューはとても旨いということ。
参考ページしっとり柔らかチャーシュー(煮豚)の作り方【おうち居酒屋】
別にお店に出すわけでも無し、必要な分だけじっくりと時間をかけて作れるので、なんならラーメン屋さんのチャーシューよりも美味しいのではと自負している。でね、まぁ毎回つけダレが余るわけですわ。

こういうものはたまに作るから良いわけで、タレを継ぎ足し継ぎ足し使うようなペースでは作らない。とはいえ捨ててしまうのはもったいないので、チャーシューを夕飯に出した翌日のわたしのお昼ご飯は記事タイトルの通りとなるわけだ。要するにチャーシューのつけダレをラーメンスープに仕立てるわけだね。
もう何回か記事にした内容ではあるのだが、作り方を若干ブラッシュアップしたので再度書いておくことにする。
チャーシューのタレって立派なラーメンスープになるんだぜ
大事な二つのポイントを先にお伝えしておこう。
一つ目は、メインの出汁は煮干しを使用し、鰹節は隠し味程度に留めておくということ。二つ目は必ず旨味調味料を入れるということ。
それでは作ってみよう。
スープさえ決まればラーメンっぽくなるから安心して
前回オリジナルラーメンの作り方をご紹介した際は、横着してタレで直接出汁を取った。が、こうしてしまうとタレと出汁の分量調節ができなくなってしまうので、ここはやはり別に出汁を取っておいた方がいいという結論に達した。

さっと昆布出汁を取ったら主役の登場だ。

これも結局好みの問題といえばそうなのだろうが…あくまでわたし個人の感覚では、かつお節でなく煮干しをメインにした方が、ずっとラーメンらしい味になると思っている。カツオ節をメインにするとどうしても蕎麦感が出ちゃうんよね。和風に過ぎるというか。


今回は煮干しオンリーだったが、ここに少量のかつお節を加えるのはアリ。少量であれば出汁に複雑さが出て寧ろいい。だがある一線を超えると一気に蕎麦化するのでご注意あそばせ。

麺や具はお好きなものを
今回乗せる具はこちら。

煮卵とチャーシューはいずれも手作りだが、余った風に見せかけて、翌日のラーメンを見越してあらかじめ取っておいたものである。フフフ…作った者の特権よ…。それと茹でた小松菜、ネギ。小松菜好きなんだよなぁ。
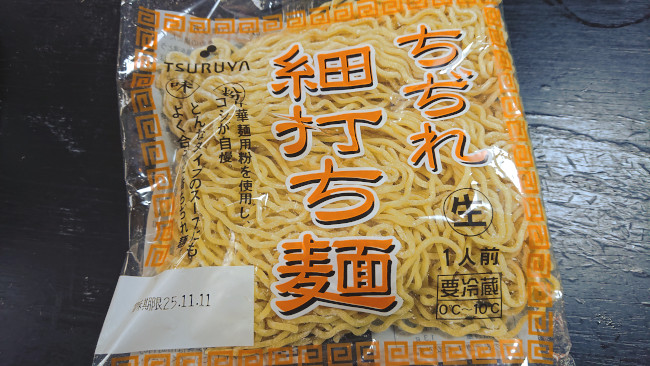
麺はいつも当たり障りのないものを買ってきてしまう。本当はね、麺も色々な種類が売っているのでこだわって選んだらいいのかもしれないけど、とりあえず今のところはこれで。
それとオマケのネギ油。

ネギの青いところが野菜室に貯まってきたところで仕込むようにしている。ラーメンに合うのはもちろん、炒め物の仕上げに回しかけてやるのもいい。普通の家にはあまり置いてないんじゃないかと思うが、もし無くても何らかの油分は欲しいところ。
そもそもチャーシューを作ると副産物として大量のラードが手に入るので、チャーシューをラーメンに乗せる前にラードでサッと炒めて、その油ごと麺にオンするというやり方がおすすめだ。

出汁とタレを自分好みの配合で混ぜ、温め、茹で上がった麺や具材と共にどんぶりに盛り付けたら完成だ。
その際には二つ目のポイント「旨味調味料」をスープに加えるのを忘れずに!
加える前と後でぜひ飲み比べてみて欲しい。上手く言えないんだけどとにかくめっっっっっっっっちゃラーメンっぽくなるから!もちろん前回記事のように鶏ガラスープを使うのもいいぞ。ほとんどの鶏ガラスープには旨味調味料が入っているし、より複雑な味のスープが出来上がる。
今回はシンプルに味の素を数振りしたが、つまりはどこのラーメン屋さんでも普通に旨味調味料を使っているということなんだろう。実に優秀な調味料ですな。
次の課題は甘味かしらね

麺はどうしても市販の感じが否めないが、スープはもう、ほとんどお店の味といっても過言ではない。でもあれね、決して名店じゃなくて、その辺の定食屋で700円ぐらいで食べられるラーメンのスープね。もちろん「その辺の定食屋で700円ぐらいで食べられるラーメン」をディスっているわけじゃないそ!そもそもこのスープはわたし自身が調理したものだし、そういうラーメンにはそういうラーメンの良さがあるのだ。
じゃあ、名店のスープと何が一番違うのかというとおそらく「甘さ」なんじゃないかと思う。
チャーシューのタレとしてちょうどいい味にチューニングすると、どうしても砂糖の甘味が強くなっちゃうんだよなぁ。それがラーメンスープ化したときにどうも安っぽく感じるのよ。砂糖じゃなくて味醂にしてみようかしら。煮込むわけじゃなくてツケダレに使うだけだから、お肉も固くならないと思うし。

タレがまだ余っていたので、翌々日は煮干し出汁にカツオ節や鶏ガラスープなどを加えて、もやし、刻みにんにく、市販のハムみたいなチャーシューなどを乗せて、なんちゃって二郎風にしてみた。こんな風に気軽にカスタマイズできるのもラーメンをオリジナルで作るメリットだろう。
というわけで、より良い作り方を発見したら再度ご報告しようと思う。
それでは。